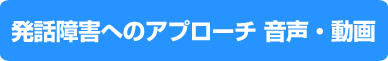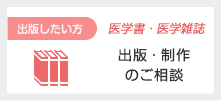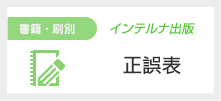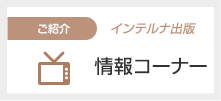発話障害へのアプローチ ―診療の基礎と実際―
監修:廣瀬 肇(東京大学 名誉教授)
著者:今井智子(北海道医療大学リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科 教授)、生井友紀子(横浜市立大学附属病院耳鼻咽喉科 言語聴覚士)、苅安 誠(京都学園大学健康医療学部言語聴覚学科 教授)、永井知代子(帝京平成大学健康メディカル学部言語聴覚学科 教授)
ISBN:978-4-900637-51-1
判型:B5判 152ページ
発行日:2015年10月15日
本書の【発話障害へのアプローチ 音声・動画】は下記からアクセスください。
内容
・“うまく話せない”“ことばがおかしい”“吃る”など、ことばの音が正しく出せない状態、すなわち「発話障害」に対して、どのように向き合っていくか!
このテーマに沿って、臨床経験豊かな執筆者たちが詳細かつわかりやすく解説。
・「実際の臨床場面での診察の進め方」により、すぐに役立つ実践的知識を記述。
・内容は「小児の構音障害」「成人の構音障害」「吃音」「発語失行」に分かれ、こうした患者さんが、耳鼻咽喉科、神経内科、小児科などをおとずれたらどうするか!?について、豊富な音声サンプル・動画(ウェブ配信)も併せて、具体的に理解できる。
・耳鼻咽喉科、神経内科、小児科など、「発話」にかかわる可能性のある各科の医師、および臨床にたずさわる言語聴覚士の必携書!
このたび、本書籍について、下記の誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。
目次
序 文
第1 章 イントロダクション―ことばと発話―
1 ことばの3 要素
2 ことばとコミュニケーション
3 ことばを話す仕組み
4 発話の障害
5 本書で取り扱う発話障害
1) 構音障害
2) 発語失行症
3) 吃 音
第2 章 小児の構音障害
1 健常児の構音発達
1) 日本語の音の仕組み
2) 構音発達
2 小児の構音障害
分類および定義
3 小児の発話障害の特徴
1) 構音障害
2) 構音障害と鑑別が必要な発話の誤り
3) 鼻咽腔閉鎖不全に伴う発話特徴
● 実際の臨床場面での診察の進め方―患者が外来を訪れた際,どのように診察を進めていくか―
1.診 察
①患者の家族の訴えを確認する(紹介状があれば内容を確認する)
②現病歴を聴取する
③既往歴・治療歴・家族歴を聴取する
④子どもに簡単な発話の検査をし,その発話特徴をスクリーニングする
⑤発語器官(構音器官)の形態と機能を観察する
⑥聴力に問題ないか,耳鼻科的な疾患がないか確認をする
⑦生育歴,発達歴を聴取し,言語発達および運動発達に遅れはないか,発話に
関連する問題がなかったか確認する
⑧歯科的な問題はないか確認する
⑨摂食機能に問題がないか問診する
⑩協調運動に問題はないか確認する
⑪以上の所見から構音障害が疑われた場合,言語聴覚士に構音の評価を依頼する
2.鑑別診断
1)機能性構音障害の特徴と対応
①特 徴
②対 応
2)器質的問題への対応
①鼻咽腔閉鎖不全への対応
②舌小帯短縮症への対応
③耳鼻科的疾患への対応
④歯科的問題への対応
3)知的障害・言語発達障害合併例への対応
4)吃音合併例への対応
文 献
第3 章 成人の構音障害
1 発話(話しことば)の要素とその障害
2 成人の構音障害
1) 器質性構音障害
2) 機能性構音障害
3)運動障害性構音障害
3 発話の異常の鑑別
4 発話障害のあらわれ方―運動障害性構音障害を中心に―
1) 声の障害
2) 鼻腔共鳴の障害(鼻音性の異常)
3) 構音の障害
4) プロソディの障害
5) 発話全般の明瞭度と異常度(自然度)
5 運動障害性構音障害の代表的タイプ別の発話障害のあらわれ方
1) 麻痺性構音障害(脳血管障害,筋萎縮性側索硬化症(ALS)など)
2) 運動失調性構音障害(脊髄小脳変性症(SCD)など)
3) 運動低下性構音障害(パーキンソン病(PD)など)
4) 不随意運動に伴う発話の障害
6 運動障害性構音障害のタイプの分類鑑別
1) 運動障害性構音障害の聴覚印象によるタイプの分類鑑別
2) 運動障害性構音障害のタイプの分類鑑別
● 実際の臨床場面での診察の進め方―患者が外来を訪れた際,どのように診察を進めていくか―
1.発話に注目した簡便な診察の実際
①問診中の聴診
②自分で簡単な発話の検査をする
③初期のおおまかな発話の障害の判断をする
2.運動障害性構音障害を疑って診察する場合の要点
1)発話に関係する器官の簡便な観察と診察
①顔面と頸部
②顎・舌・口蓋帆・咽頭
2)咽頭喉頭のファイバースコピー下の簡便な観察と診察
①鼻咽腔
②喉 頭
3) 運動障害性構音障害の鑑別診断
文 献
第4 章 吃 音
1 吃音と吃音症
1)音声言語症状
2)身体随伴症状
3)心理的反応
2 吃音の症候
3 小児と成人の吃音
1)小児の吃音
2)成人の吃音
4 吃音の発症率と有病率
5 吃音の合併症
6 吃音を有する人たちの心理・精神
7 吃音症の重症度と進展段階
1)重症度
2)進展段階
8 吃音症の起源
9 吃音症の治療
1)言語療法
2)薬物療法
3)心理療法
10 吃音症に対するケア
1)小児での環境調整
2)成人での環境調整
3)セルフ・ヘルプ・グループ
● 実際の臨床場面での診察の進め方―患者が外来を訪れた際,どのように診察を
進めていくか―
1.診 察
①小児の診察
②成人の診察
③身体・神経学的評価と病歴聴取
④吃音歴の聴取
⑤音声言語・発話行動の評価
⑥発話の分析
2.診 断
①診 断
②鑑別診断
3.症例への対応―本人・家族への説明
①吃音症である・吃音症でないことを伝える
②予後と治療方針を説明する
③誤った認識を修正する
④今後の対応を決める
文 献
第5 章 発語失行
1 発語失行とは
1)歴 史
2)日本における位置づけと最近の欧米の動向
3)発語失行の定義
4)病因と頻度
2 発症メカニズム
1)心理言語学的モデル
2)発話の脳内ネットワークと責任病巣
3 神経変性疾患による発語失行(原発性発語失行)
1)原発性進行性失語の臨床型と原疾患
2)進行性発語失行の臨床像と病巣
4 小児発語失行(発達性発語失行)
1)成人における発語失行との違い
2)小児発語失行と遺伝子障害
● 実際の臨床場面での診察の進め方―患者が外来を訪れた際,どのように診察を
進めていくか―
1.言語症状のみかた
1)診察中に得られる所見
①発語はあるか
②失語のサインはあるか
③構音障害はあるか
2)神経心理学的検査で得られる所見
①失語の有無に関する簡易検査
②標準的な失語症検査バッテリーの使用
③ AOS の検査
④ PAOS の検査
2.随伴症状のみかた
①口部顔面失行
②肢節運動失行
3.病 巣
① AOS をきたす脳部位
②頭部MRI のみかた
4.鑑別診断
5.臨床経過・予後
①急性発症疾患の場合
②神経変性疾患(PAOS およびPPA-G)の場合
6.治 療
①急性発症疾患の場合
②神経変性疾患の場合
7.症例呈示
8.今後の診療に向けて
文 献
[ウェブ配信] 音声・動画ファイル一覧
索 引
監修者・執筆者略歴
Note 一覧
離散的から連続的へ
内科学における構音障害の定義
機能性構音障害
発達性発語失行(developmental apraxia of speech)
共鳴(resonance)
鼻咽腔閉鎖不全を引き起こす疾患
鼻咽腔閉鎖機能の評価方法
正常発達の指標
構音の評価
構音訓練のゴール
口腔内圧を高める訓練
口腔筋機能療法(oral myofunctional therapy:MFT)
自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorders:ASD)
注意欠如/ 多動性障害(attention deficit/hyperactivity disorder:ADHD)
神経・筋疾患に起因する発話の障害=運動障害性構音障害という記述について
痙性と固縮の違い
聴覚印象:自発話とGRBAS 評価
声の高さの異常による障害例
中枢神経系異常に基づくと考えられる,特殊な音声障害―痙攣性発声障害と
本態性音声振戦症―
声帯麻痺について
鼻咽腔閉鎖不全を聴く・視る
“音の誤り方の一貫性”と“音の誤りの起こり方の一貫性”
発話のリズム
流暢という用語の使い方
多系統萎縮症(mulltiple system atrophy:MSA)
断綴性発話(scanning またはscanned speech)
パーキンソン病における声
自発話を引き出すために
口腔内のチェック
発話と歩行
発話とCSSB
病的反射と(深部腱)反射の亢進
発声以外の動作で鼻咽腔閉鎖を診る重要性
顕在overt と内在covert
発話の流暢性 (speech fluency)
ヒトが話すことの背景の説明
喉頭の内視鏡的観察
課題による発話の自動性と自由度
発話の分析
吃音症stuttering の診断
失 行
Broca 失語
神経変性疾患
運動前野
音節と音素
錯語と錯書
foreign accent syndrome
Coffee Break 一覧
きょうだいで同じ構音障害?
双子語がある?
舌足らずとは?
日本語の訛りと方言
ろれつがまわらない
発話の障害について各診療科に期待されること
英国王のスピーチ(The King’s Speech) 2010 年イギリス映画
流暢・非流暢の分類
遺伝子がありすぎてもダメ?
ミラーニューロンと言語